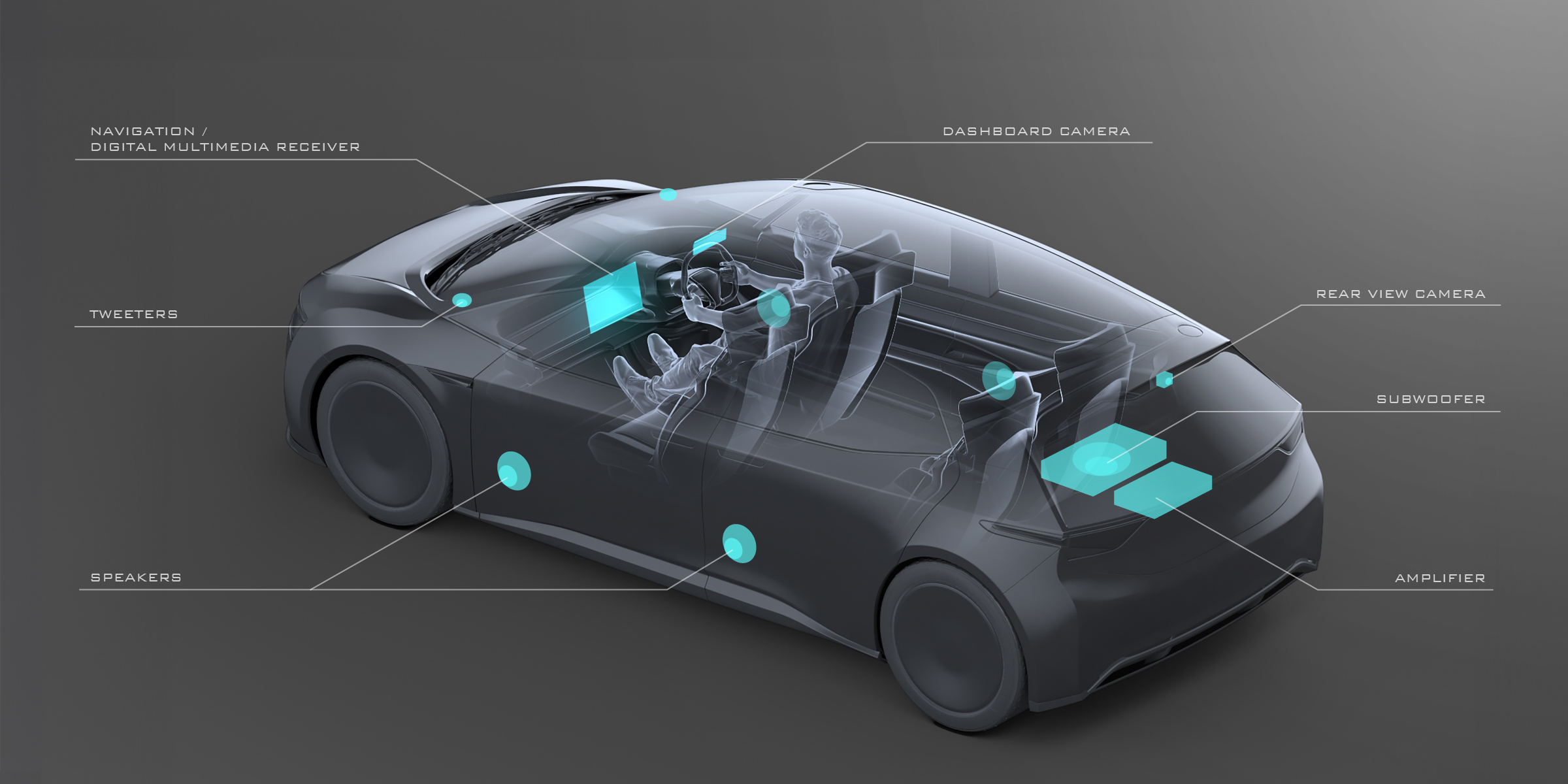プロダクトやブランドのデザインを中心に、幅広い領域のデザインを実践しているJVCケンウッド・デザインでは、領域の枠にとらわれないプロジェクトに取り組む上で、多様性のある職場づくりを心がけています。新たなデザイン領域にチャレンジしていくキャリアパスや、異なる専門性を持つメンバーとの情報共有、国際色豊かなデザイナー同士のコラボレーションなど、JVCケンウッド・デザインが体現する多様性のあり方について、5人のデザイナーが語り合いました。
異なる領域のデザインに共通性を見出す
JVCケンウッド・デザインでは、社内のキャリアパスの中で異なる専門性を身につけていく働き方を実践しています。渡辺さんは現在ビジョンデザインなどの広義のデザインを実践されていますが、どのようなキャリアを重ねていったのでしょうか?
渡辺 私はもともと入社時はプロダクトデザイナーとして採用されたのですが、3年目からビデオカメラの操作画面のデザインを担当することになり、それ以来UIデザインが仕事の軸になっています。現在担当している技術の研究開発や新規事業開発プロジェクトにおいても、UIデザインの知見を活かしながら実践している感覚がありますね。
プロダクトデザインからUIデザインの領域に移る際に苦労はありましたか?
渡辺 後任としてアサインされた当時は、ゼロベースで仕事に取り組まなくてはならなかったので、なかなか大変ではありましたね。とはいえデザイナーとして負けずぎらいなところがあるので、当時ビクターの社内で取り扱っていたテレビ製品のデザインを担当している先輩にインターフェースのデザインについて教わりながら、なんとか乗り越えていきました。いま振り返ると、そのころはiPhoneが発表されたばかりであり、スマートフォンアプリの開発がどんどんおもしろくなっていくタイミングでもあったので、その頃からUIデザインに関わることができたのはよかったなと思います。

JVCケンウッド・デザインが取り組んでいる広義のデザインの実践例として、デザイン思考のワークショップがあります。ワークショップのファシリテーターは、様々な領域のデザイナーが経験されるそうですが、どのような意識で取り組んでいますか?
有本 社外の企業や組織に対してデザイン思考ワークショップを実施することもありますが、JVCケンウッド本社人事部と共同で定期的に実施しているワークショップでは、デザイナーがファシリテーターとして参加しています。JVCケンウッド・グループとしてもデザイン経営推進の一環でデザイン思考を業務で活用する方針があるため、デザイナーそれぞれがワークショップについて研究しながら実践しています。
その中で、「ワークショップデザインではUXが重要」といったことはよく話していますね。ワークショップのゴールを見据えながら、参加者に対してどのような価値を提供できるのかを考える点では、製品やサービスのデザインとも共通性を感じます。最近では有志を中心にワークショップデザインの知見を共有する場が生まれはじめていて、それぞれの現場で実践してきた手法や考え方についてみんなで話し合い、次のワークショップデザインやファシリテーションに活かしています。

沼野 そういった本社人事部と共同開催している研修のほかにも、事業部門や関係会社の方々の抱える「もやもや」や課題に対して、ワークショップを計画し、言語化のお手伝いをするなど、デザインの力で課題解決をおこなう様々な活動に取り組んでいます。
例えば、プレゼンテーション資料の整理から発展した「伝える力の強化活動」ワークショップでは、どのような人に向けた、なにを伝えたいプロジェクトなのかを確認するために、じっくりとヒアリングする機会を設けています。ただ資料を綺麗に整えるだけでは根本的な課題解決にはつながらないので、お話ししながら一緒に解決の種を見つけていくような、相手を巻き込みながら取り組んでいく、共創の視点を大事にしています。

国際色豊かな職場だからこそ生まれるデザインの実践
JVCケンウッド・デザインは国内だけではなく、外国籍のデザイナーが所属していることも特徴です。ヒョンジュンさんは韓国、アルワさんはインド出身ですが、どのようなきっかけで入社されたのでしょうか?
ヒョンジュン 私は大学でインダストリアルデザインを学んでいたのですが、韓国のデザイン教育機関が実施している産官連携プログラムに参加し、JVCケンウッド・デザインの方々と一緒にプロジェクトを実施する機会がありました。その際に新しいデザインプロセスに触れ、たくさんのことを学びました。こんなに多様な領域のインハウスデザイナーが所属しているデザイン会社はなかなかないと感じ、卒業後に入社することを決めました。
アルワ 私は大学と大学院でインダストリアルデザインを学び、大学院の時に3ヶ月間JVCケンウッド・デザインのインターンシップに参加したことがきっかけでした。その際、カメラのアイデアを考えるプロジェクトに参加したのですが、日々様々なチームのメンバーの方々とお話ししながら、JVCケンウッドの文化はもちろん、日本の文化にも触れることができた経験がとてもおもしろくて、卒業後に移住して就職することを決めました。
ちなみに、韓国とインドのデザイナーはどのような仕事を目指す方が多いのでしょうか?
ヒョンジュン それぞれ目標や専攻分野が異なるため一概には言えませんが、私の周りでは、自分のキャリアプランに沿ってインハウスデザイナーの道に進む人もいれば、デザイン専門会社に就職する人もいます。

アルワ ここ最近は「Made In India」の製品を手がけるインド国内のメーカー企業が増えてきているので、インハウスデザイナーを目指したり、クリエイティブエージェンシーに就職したりする人が多いですね。
国籍の異なる方と一緒に働く中で受ける刺激はありますか?
アルワ あると思います。普段の仕事の会話はもちろん、仕事以外のカジュアルなやり取りのなかで意見交換をすることが多いので、そういった場面でそれぞれの文化や考え方について知ることができる経験が、仕事にも活かされていると思います。
ヒョンジュン 海外向けのプロジェクトでアルワさんと一緒にマーケティングリサーチを担当することがあるのですが、打ち合わせの度に、私がこれまで当たり前だと思っていた価値観や文化の違いに気づくことが多く、固定観念が覆される感覚がありますね。
有本 最近では海外向け製品のOEMなど、グローバルに展開するプロジェクトが増えてきているので、先入観だけでデザインに取り組むのではなく、現地の方々の考え方を取り入れていくために、JVCケンウッド・デザインのデザイナーがマーケティングを担当する、「デザインマーケティング」に取り組む事例が増えてきています。
一般的なマーケティングとの違いはどのような点にあると思いますか?
アルワ トレンドはもちろん、ユーザーがなにを考え、どのようにもの欲しているのかを考えるのがデザイナーの仕事なので、ユーザーエクスペリエンスを軸にマーケティングを実施する点で大きな違いがあると思いますね。

ヒョンジュン そうですね。戦略的に商品のあり方について考えていく一般的なマーケティングとも重なる部分がありつつ、リサーチの段階からカラーバリエーションといった専門的な部分についても考えはじめるところに、JVCケンウッド・デザインのデザインマーケティングの特徴があると思います。
デザイナーの知見を共有し合う「DESIGN MIRAI」「クリエイターズミーティング」
様々な領域のデザイナーが働くJVCケンウッド・デザインだからこそのナレッジ共有や、それぞれが取り組んでいるプロジェクトを発表する機会として、年に1度開催している「DESIGN MIRAI」と、毎月開催している「クリエイターズミーティング」があります。それぞれどのように運営されていますか?
渡辺 年に一度開催しているDESIGN MIRAIは、JVCケンウッド・デザインの独自研究と、本社の事業部の方々と新しいデザインの提案に取り組んだプロジェクトを展示するイベントです。デザインの視点から未来の生活を想像し、どんな可能性が感じられるのか、様々なプロジェクトを通して共有し合う場として、2016年から続けています。
一方で、2020年のコロナ禍をきっかけにスタートしたクリエイターズミーティングでは、日々様々なプロジェクトで実践しているデザインプロセスを共有する場として、毎回多様な議論が生まれています。毎月1時間半実施しているのですが、最近は時間内に収まらなくなってきていますね。とはいえ業務の負担にならないように、気軽に参加できる場として続けていきたいと思っています。
ほかにも、社内でナレッジ共有ツールを使って情報共有をするようにしていて、それぞれが見に行った展示会の情報などを、社内のデザイナーたちが自由に書き込める場として活用しています。
アルワ こういった共有の場があることで、社内で実践されている様々なデザインプロセスについて触れることができますし、かならずしも直接仕事に関連のある内容でなくても、なにか自分の仕事に活かせる視点はないだろうかと考えることで、間接的な学びが得られる場になっていると思います。トレンドリサーチや展示会についての情報共有から、仕事のインスピレーションをもらえることもあります。
ヒョンジュン やっぱり普段みんな忙しく働いていますし、隣に座っているデザイナーがどんな仕事をしているかわからないこともあるので、みなさんの考え方やデザインプロセスについて知ることができる時間があるのはうれしいですね。こういった場があるからこそ、様々な領域のデザイナーがいるJVCケンウッド・デザインで働くことの魅力を感じることができていると思います。
デザイナーとしての可能性を広げる働き方への挑戦
最後に、JVCケンウッド・デザインのデザイナーとして今後挑戦していきたいことをお聞かせください。
沼野 クリエイターズミーティングのような場でみなさんのお話しを聞いていていると、入社時に持っていたスキルの領域を超えていくことで、よりデザイナーとして発想を広げていけることの可能性を感じます。私自身、プロジェクトを通じてこれまで学んでこなかったデザイン領域に触れ、様々な気づきを得る体験をしているので、今後も自分の活動の幅を広げていけるような仕事の取り組み方を実践していきたいと思います。
ヒョンジュン 本社から独立したデザイン会社であることが、JVCケンウッド・デザインの大きな特徴だと思います。JVCケンウッド・グループの仕事はもちろん、産学プロジェクトや他のクライアントとのプロジェクトに取り組んでいくことで得られる学びもたくさんあり、様々な視点を取り入れることがプロダクトの完成度を上げることにもつながっています。まずはプロダクトデザイナーとしてプロジェクトをちゃんと一人でこなせるようになることを目指しながら、これからも興味を持ったことにチャレンジしていきたいですね。
渡辺 これまでデザイナーとして20年ほどのキャリアを重ねてきましたが、これからもクリエイティブであり続けたいなと思っています。そのためには、自分の専門性を突き通すだけではなく、様々なことを学ばなくてはならないのを感じていますし、現在チームリーダーを務める中で必要な伝える力やチームを束ねる力を磨きながら、JVCケンウッド・デザインに所属するデザイナーのそれぞれの個性が活かせるような存在になりたいなと思っています。
有本 最近は経営や事業の上流におけるデザイン支援など、広義のデザインに取り組むプロジェクトが増えてきたことで、幅広い領域をカバーすることが求められるようになってきました。その一方で、注力分野が分散し、会社としての特長が薄くなっていくこともあると思っています。デザイナーとしてクリエイティブな仕事が好きでこの会社で働いているので、JVCケンウッド・デザインをおもしろい会社にしていくにはなにができるかを考えながら、様々な働き方を実践していければと考えています。
アルワ 歴史の長いJVCケンウッド・グループとしてクリエイティブであり続けるためには、ものづくりの視点だけではなく、これからどのようなものがユーザーに求められるのかを考えていくことがより必要になっていくと思います。JVCケンウッド・デザインは、「Forest Notes」のようなサステナビリティの実現を目指す自社プロジェクトなど、様々な取り組みを行っているので、これからもデザイン思考を発揮しながら、現在取り組んでいる領域に留まらない仕事に挑戦していきたいと考えています。
Profile
- Rikako Watanabe
-
- Takuya Arimoto
-
- Miki Numano
-
- Hyungjun Kim
-
- Arwa Borsadwala
-