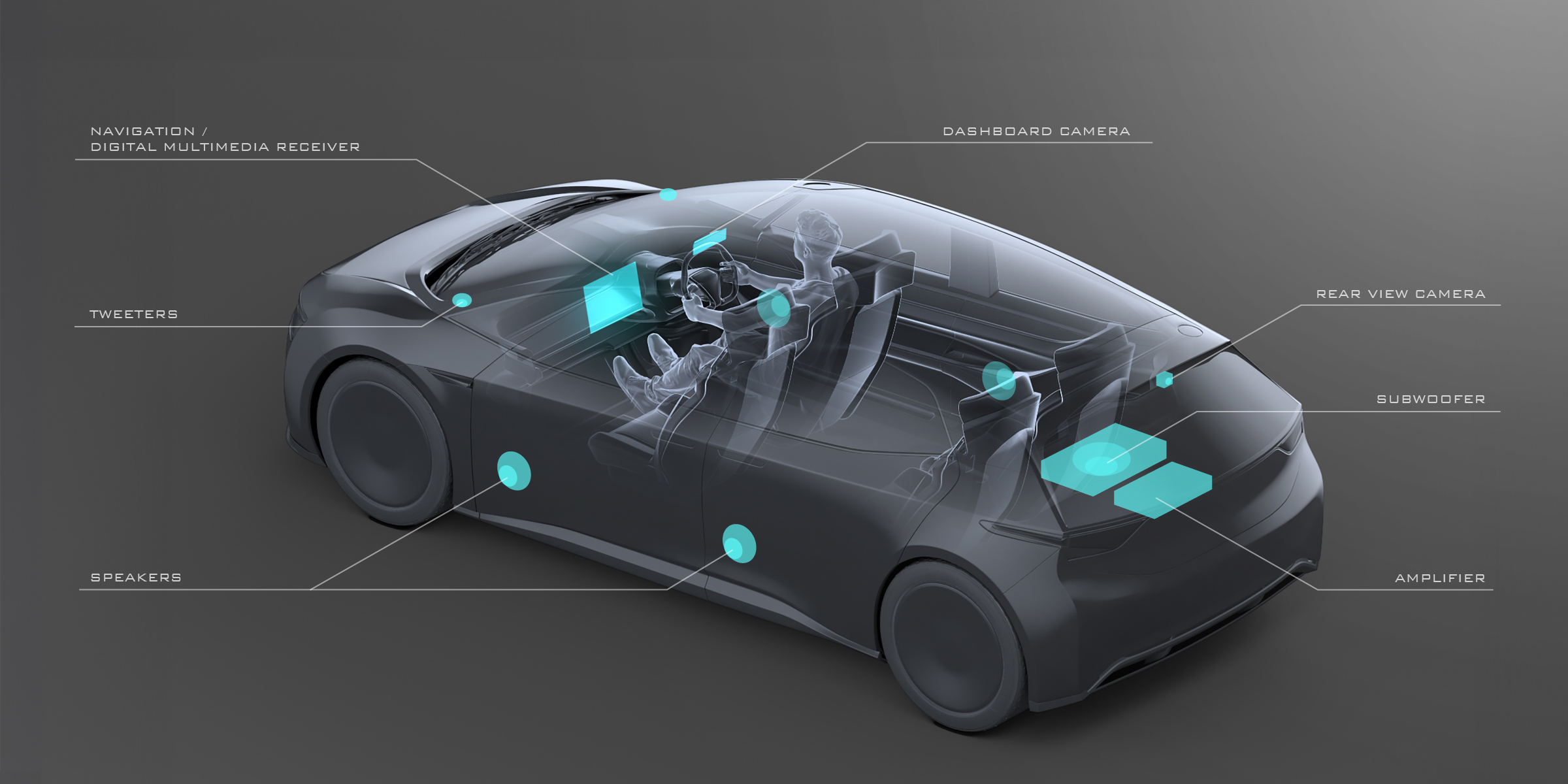JVCブランドが海外市場向けに展開しているプロジェクター「DLA-NZ500/DLA-NZ700」は、JVCケンウッドグループが独自に開発した反射型液晶素子を使用した「D-ILA」シリーズの2024年モデルです。ネイティブ4K対応プロジェクターとして世界最小サイズを実現し、国際的に権威のあるデザインアワード「iF DESIGN AWARD2025」のプロダクト分野を受賞することができました。製品開発においては、商品企画・エンジニア・デザイナーが一丸となって技術の開発から筐体のデザインまで取り組んでおり、シリーズを通じてJVCケンウッド・グループとして一貫した制作体制が実現しているプロジェクトでもあります。本製品の開発プロセスについて、JVCケンウッドエンタテインメントソリューションズ分野メディア事業部商品企画部の那須と、JVCケンウッド・デザインの大橋が振り返りました。
JVCブランドの技術が詰まった象徴的なプロジェクターシリーズ
はじめに、本製品の開発背景についてお聞かせください。
那須 JVCブランドでは、D-ILAという独自の反射型液晶素子を使ったプロジェクター製品をつくり続けており、最初のモデルが開発された1997年から現在にいたるまで、脈々とシリーズのアイデンティティが引き継がれてきました。本製品の開発においては、D-ILAの素子を活かしながら光源をレーザー化し、エントリーモデルとしての小型化に挑戦しています。
レーザー化はシリーズのフラッグシップモデルにおいてすでに実現していましたが、製造・調達コストの観点から、エントリーモデルの価格帯に見合う製品を開発できていませんでした。一方市場では、競合他社が手に取りやすい価格のネイティブ4Kプロジェクターを展開しているため、シェア拡大を狙うためにも、エントリーモデルの製品開発をゼロからスタートさせたんです。

まずはどのようなことから開発に着手されたのでしょうか?
那須 まずは光学ユニットをはじめとする、プロジェクター内のすべての回路基盤を再設計することからはじめました。これまでのシリーズでは、光学ユニットの大きさによって筐体の高さがある程度決まってしまっていたので、光学ユニットの小型化を目指すと同時に、電源回りやプロセッサーなどの高さもできるだけ抑え、筐体をコンパクトに収める設計に取り組みました。
そういったエンジニアリングの部分に関しては、同じJVCケンウッドグループ 内で進めていくのでしょうか。
那須 そうですね。プロジェクターの製品開発の場合、われわれ本社の商品企画がどのような製品をつくりたいのかを考え、グループ内のエンジニアとデザイナーにインプットします。要素開発から筐体設計まで、すべてをインハウスで制作できていることは、われわれが開発するプロジェクターの強みだと思いますね。他のメーカーを見渡してみても、ここまで高い自由度で製品を仕上げていくことができる企業はなかなかないと思います。
デザインのプロセスはどのようにはじまるのでしょうか?
那須 JVCケンウッド・デザインの大橋さんには、新設計したパーツをシャーシの中に組み込んだ段階からプロジェクトに参加してもらいました。まずは5パターンほどのラフスケッチを制作してもらい、過去のモデルにかなり忠実に沿ったようなものから、まったく異なるかたちまで、さまざまなアイデアをいただきました。それらを社内のエンジニアと営業企画、場合によっては事業部長を巻き込んで検討し、大体の方向性を集約していきます。
大橋さんはラフスケッチをはじめ、デザインプロセスに取り組むにあたってどのようなことから考えはじめましたか?
大橋 僕はこれまでに左右独立型のワイヤレスイヤホンやヘッドホンなどのデザインを担当してきたんですが、そういった製品は機能的な使いやすさだけではなく、どちらかというとファッション性やライフスタイル商品としてのキャラクター性や魅力をいかに出せるかを考えることが多かったんですね。一方でプロジェクターは、持ち歩くものでもなく、ただ空間に鎮座している静的な存在のため、最初はデザインの手がかりがまったくなくて、なにから考えればいいのかがわからない状態でした。
なので、まずはこれまでシリーズのデザインを担当されたデザイナーの先輩方から、歴代のモデルの開発にあたっての考えをまとめたものや、デザインの途中経過の手書きスケッチなど、現存する資料をたくさん集めていただき、シリーズのアイデンティティについての理解を深めることにまずは時間を使いました。

社内に資料が保存されていたのでしょうか?
大橋 そうですね。すでに引退されたデザイナーの方が制作したデザインフィロソフィーに関する資料も含めて、社内に残っている資料をかき集めていただき、先輩方が当時どのようにデザインしていたのか、直接聞いて回ったんです。D-ILAはJVCブランドの技術が詰め込まれた、ブランドにとって象徴的なシリーズの一つなので、担当していたデザイナー方々の思い入れが強く、デザインするにあたってなにを知っておくべきなのかを教えていただけたことは大きかったですね。
那須 こだわりが強い先輩方ばかりでしたからね(笑)。実際にプロジェクターの販売店にも行ったんでしょう?
大橋 そうですね。最初はデザインの手がかりを探りにいったんですが、ちゃんとした視聴室でD-ILAの先代モデルを体験し、思っていたよりも数倍映像が綺麗なことに驚きました。
黒の深さが圧倒的で、ほぼ真っ暗な映像の中に、黒からダークグレーまでの繊細な諧調と、空間としての奥行きを感じられて、没入感がすごいなと。何度も観たことのある映画でも、まったく違う印象を受けるんじゃないかなと思います。プロジェクターという製品は、オーディオのようにマニアックな世界だと思っていたんですが、D-ILAシリーズには説明不要の魅力があることを実感できたのは、スケッチを描き始める前のモチベーションを得る機会としてよかったですね。
「なるべくしてなった姿」をデザインする
過去の資料を通して感じた、シリーズのデザインフィロソフィーとはどのようなものでしょうか?
大橋 プロジェクターの筐体は、光学ユニットをはじめとする内部のさまざまなパーツによってある程度かたちが決定されてしまうためデザイナーのスケッチがそのまま商品に反映されることはあまりないのですが、 柔らかい考えのまま描かれたスケッチをたくさん見るうちに、シリーズのアイデンティティについて徐々に理解できるようになっていきました。
D-ILAシリーズは一貫して、レンズから真っ直ぐに放出される光軸を意識したデザインが大きな特徴です。プロジェクターという存在は、ただひたすら美しい映像を放出するだけの物体なので、作為的なかたちを取り入れず、レンズから放射される光の軸と機体を冷やすための空気の流れに沿った造形を目指し、「なるべくしてなった姿」をデザインすることが、シリーズのデザインフィロソフィーとして共通している考え方だと思います。
D-ILAシリーズは高価格帯の製品ですし、究極の映像美を体感したいお客様に向けた尖った商品だといえます。本製品においても、映像美を追求する本物志向の製品に相応しい、純粋な造形アプローチをとることで、性能の素晴らしさをノイズなく感じてもらえるたたずまいを目指そうと考えました。

具体的な造形要素について、それぞれどのように検討されたのかを教えてください。
那須 本製品は、機体を冷却するための吸排気のシステムが一新されているのも特徴で、先代のモデルでは製品の前面から排気していたところ、本モデルでは前方から空気を吸い込み、後ろで排気を出すシステムになっています。そのため、以前はレンズに排気が被らないように採用していた縦型のフィンを横型のフィンに変更しており、新しい製品の顔つきになっていると思います。
大橋 デザイナーとしては、前面から排気している先代モデルの顔を踏襲すればシリーズとしての統一感が出せるだろうと思っていたんですが、吸排気システムが変わったことにより、顔づくりを似せることができなくなってしまいました。ただ、統一感を出すために、機能に合っていない表面的な造形を取り入れてしまうと、シリーズの考え方からは離れてしまいますし、本物志向の製品にふさわしくないデザインの方向に進んでしまいます。
そのため、かたちを似せることは諦めて、シリーズの原点である光軸表現や、新しいエアフローに合わせた純粋な造形をつくることに立ち返ったんです。僕らはよく「本物感のあるデザイン」と呼んでいるんですが、形状はまったく別のものではあるものの、雰囲気や佇まいに、シリーズのアイデンティティを継承できるようなデザインを目指しました。
「なるべくしてなった姿」をデザインする上での大変さはどこにありましたか?
大橋 まるでレンズから放出される光軸と筐体を通り抜けるエアフローが感じられる、シンプルな印象のデザインにするために、たくさんの配慮が詰まっているところですね。プロジェクターは光が投射されるレンズが主役の製品なので、それを引き立たせるミニマムなデザインを心がけています。前後左右シンメトリーの造形に仕上げたのは、光の直線以外の方向感が生まれないようにするためであり、実際に製品を天吊の状態で室内に取り付けた時にいかに空間と調和できるかを考え、製品の曲線によって生まれる陰影が、美しく滑らかなグラデーションになる造形をデザインしています。
角R(アール)に関しては、さっとコンパスで引いただけのように見えたとしても、実際には異形のスプライン曲線を使用しています。ただ、それだけだと垂直面が食パンのように凹んで見えてしまう錯覚現象が起きるため、最終的に10,000Rの円弧を側面につけ、視差を発生させることでシンプルに見えるようにしているんです。
これは箱物をデザインする上での特徴なんですが、側面をそのまま円弧状にカットすると、斜めから製品を見た時に、目の錯覚で側面が飛び出して見えてしまう現象が生じます。それを回避するためには、円弧ではなくアプローチRをつける必要があるんですが、通常のアプローチRでは”デザインされた感じ”が残ってしまい、シンプルな印象からは離れてしまいます。そのため、デザインの手がかりが残らないRの追求に時間をかけました。まっすぐに見せるために曲げたり、曲線に見せるために異形にしたりと、本製品のデザインはそういった工夫の集合体だといえます。

互いの意見を主張し合いながら製品をまとめ上げるプロセス
那須 デザインのディテールについては、自分で考えているのか、誰かに教わるものなの?
大橋 同シリーズの担当者に限らず、幅広い方々にアドバイスをいただいています。錯覚を補正するための知見が歴代の先輩デザイナーたちの中に蓄積されていたので、「ここはこうした方がいい」と通りがかりにアドバイスをくれました。このシリーズは特に思い入れの強い方が多いですし、プロジェクトに集中できる環境をつくっていただけたので、じっくり向き合うことができたと思います。
那須 なるほど。社内で注目のプロジェクトだったからね。こうしてあらためてこだわりについて聞くと、製品への愛着がさらに沸きますね。歴代のシリーズの中でもとりわけクリーンなデザインですし、僕自身シンプルなデザインが好きなので、この仕上がりには大満足です。最初に作成したデザイン依頼書にも「飽きのこないデザイン」という言葉を書いていて、製品ができあがった姿を見た時には、大橋さんと馬があったのかなと感じました。大橋さんとプロジェクトを進めるのは今回がはじめてでしたが、仕事に向き合う上でのストイックな姿勢に大きな信頼を寄せていました。
飽きのこないデザインを実践する上ではどのような工夫が必要でしたか?
大橋 飽きのこないロングライフデザインを実現するため、機能に対して素直で明快なモチーフを大切しています。直線や円などシンプルな要素を組み合わせると、曲率差によって意図しない陰影や形状が歪んで見える錯覚が生まれやすいため、最小限のアプローチRなどを全体にさりげなく取り入れることで、シンプルでありながら、造形にノイズの少ない普遍的なデザインを目指しました。
ちなみに先日、歴代の製品と本製品を並べていた時に、たまたま立ち寄った本社のマーケティングの方が、「境界線が見えないですね」とおっしゃっていて、「ちゃんと伝わっているんだな」と、少し自信を持つことができましたね。
そういったデザインについての議論を進める中で、同じグループ内にエンジニアチームがいるからこそ生まれたコミュニケーションはありましたか?
大橋 どのような製品のプロポーションを目指したいのかを考えた時に、設計に関する要望をこちらから出させていただいていました。最終的にかたちを整えていく時には削り代が必要になるので、レンズや光学ユニットといった内部の機構を極力中心線に寄せて、モジュールが側面に散らないようにお願いしました。
那須 そうでしたね。われわれ商品企画とデザイナー、エンジニア、営業のみんなが、お互いの領域を主張し合いながら、一つの製品にまとめ上げることができたプロジェクトだったと思います。コストの面でさまざまな制約がありましたが、大橋さんが粘ってくれたことで実現した部分も多々あります。エントリーモデルとはいえ高価格商品ではあるので、ラインアップとしてのポジションを維持できるデザインに仕上げてもらいました。
大橋 同じシリーズのフラッグシップモデルと比べた時に、廉価版のような見た目にならないようにしたいという思いはありましたね。むしろ、フラッグシップモデルのコアな部分を抽出した、純粋なモデルとしてのたたずまいのデザインを目指しました。

海外展開を意識したアイデンティティの構築
本製品はおもに海外市場向けに展開されていますが、デザインに取り組む上で海外を意識する場面はありましたか?
那須 海外販社の方々とは、ファーストスケッチの段階からどのようなかたちになるのかを共有しています。その後の各プロセスにおける、スケッチとモックアップも共有しているので、海外販社の方々はもちろん、実際に販売する現場の方々の意見をいただきながらデザインを仕上げていきました。JVCブランドの場合、売上の約9割がアメリカと欧州のため、海外販社の方々からの意見は外せないですね。
また、国内と海外のユーザーを比べると、製品の取り付け方が大きく異なる特徴があるため、海外市場向けの製品開発においては、その点を意識してデザインすることが多いです。国内では据え置きと天吊りの使用比率は約半々ですが、海外の場合、約9割のユーザーがプロジェクターを天吊りで使用しています。さきほど大橋さんから話があった、天吊りで取り付けた際の陰影の美しさを意識した造形は、海外のユーザーの使用環境を意識しているからこそのデザインでもあるんです。
開発プロセスにおいて、海外販社の方々からはどのようなフィードバックをもらうことが多いですか?
那須 これまでのシリーズのファンに向けて売りたいという意向は大きいので、従来のモデルと比べても一目でJVCブランドだとわかるデザインを一貫して求められています。やはりセンターレンズが強調された光軸表現はシリーズのアイデンティティなので、海外販社の方々からもその点について意見をいただくことが多いです。
iF Design AWRD 2025の受賞を振り返ってみていかがですか?
大橋 製品の価値自体は間違いないと思っていたんですが、映像の綺麗さについてはなかなか伝わりにくいですし、デザインにおける目新しさを表現するのが難しいジャンルだと思うので、総合的な完成度を評価していただけたのはよかったですね。 iF DesignAwardは欧州においてとてもプレゼンスの高い賞ですし、国内ではシリーズとしては久しぶりにグッドデザイン賞を受賞することができました。世界中の専門紙でも非常に高い評価をいただいています。
最後に今後開発に取り組んでみたい製品についてお聞かせください。
那須 個人的にはさらにハイエンドのモデルをつくってみたいですね。ホームシアターの最高峰としてのポジションをあらためて確立できるような、誰が観ても最高の映像だと感じられる製品開発に取り組みたいと思います。
大橋 D-ILAの映像技術を盛り込んだ上で、量販店でも販売できるようなエントリー製品をいつかつくってみたいなと思いますね。こういった本物志向の製品に興味を持ってもらうためにはどうすればいいのか、もう一度考えてみたいなと。会議室での使用や生活に馴染むものではない、D-ILAのプロジェクターシリーズの違いが感じられる製品デザインに挑戦してみたいと思っています。
Profile
- Kohei Ohashi
-
- Product Design
- Hiroto Nasu
-
- JVCKENWOOD Product planning