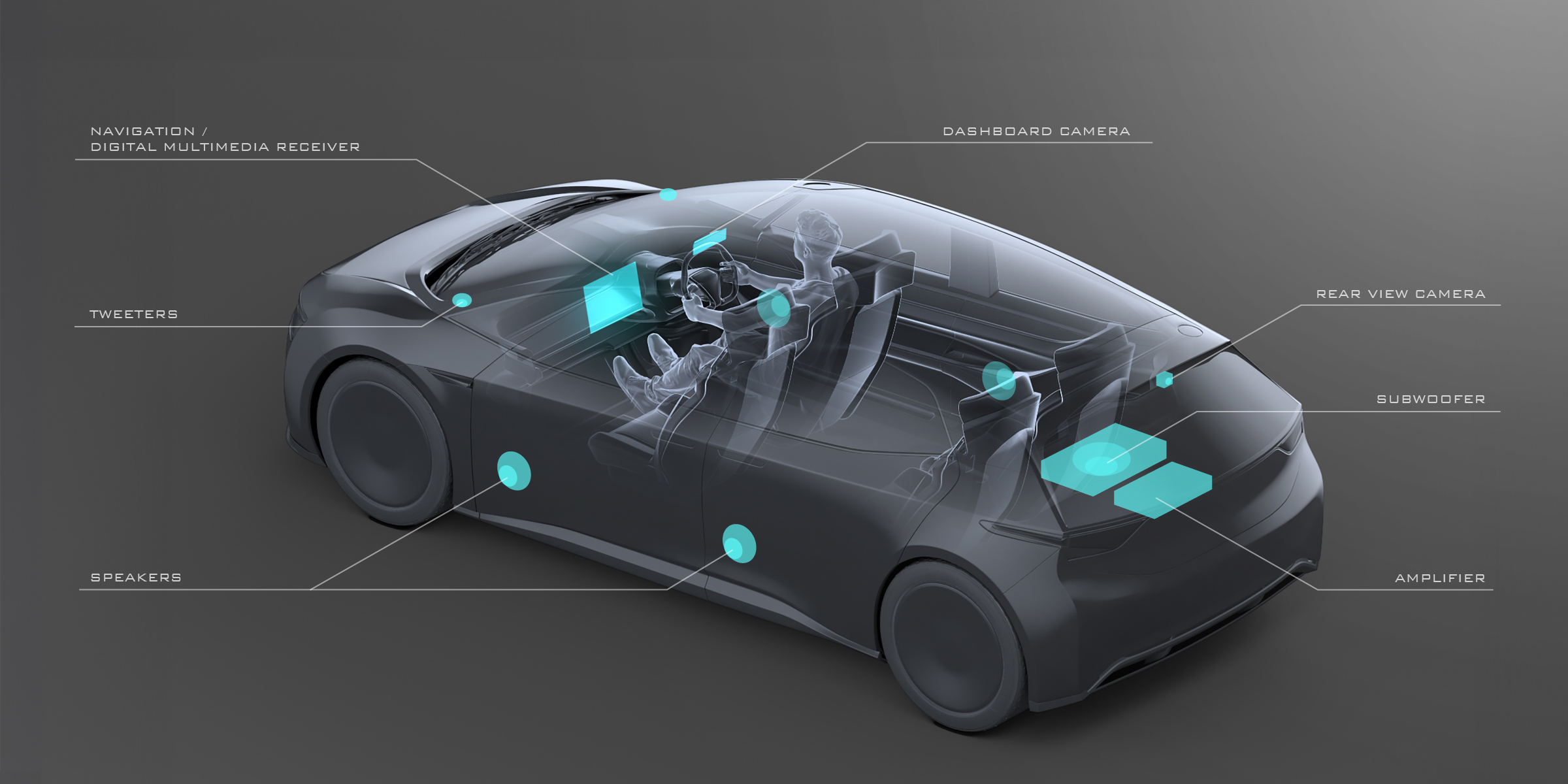JVCケンウッド・デザインでは、入社1〜2年目の社員を対象に、新しいテクノロジーをユニークな発想で使いこなしたオリジナル作品の展示とデモンストレーションをおこなうイベント「Maker Faire(メイカーフェア)」に出展する自社プロジェクトを、2018年より継続しています。プロダクトデザインに限らず、多様な専門性を持つ社内のデザイナーたちの共創の場として、これまでに様々なユニークな作品が生み出されてきました。
2024年9月21日(土)と22日(日)の2日間、東京ビックサイトで開催された「Maker Faire 2024」では、5名のデザイナーがプロジェクトに参加し、「新しい音の体験」のデザインに取り組みました。企画立案からプロトタイピング、さらに協力会社との共創による実装にいたるまで、すべての意思決定を経験したプロジェクトの裏側について、5名のメンバーが振り返ります。
それぞれの専門性を発揮しながら「新しい音の体験」をデザイン
JVCケンウッド・デザインは2018年から毎年Maker Faireに出展していますが、2024年度はどのようなテーマで取り組んだのでしょうか?
森 Maker Faireに出展する上で、JVCケンウッド・デザインでは「デザインを活用して音と映像の楽しさを子どもたちに伝えること」を目標として掲げています。それに加えて毎年異なる制作テーマが用意されているのですが、2024年は「様々な人が楽しむことができる新しい音の体験」に取り組みました。
役割分担はどのように決めていきましたか?
赤池 みんながやりたいことを基準に、それぞれの専門性を発揮していくうちに自然と役割が決まっていった感じでしたね。僕は大学でインタラクションや体験のデザインについて学んでいたので、大型ディスプレイでの画面遷移や、体験全体の流れを考えていきました。
森 私はおもにスケジュールや予算の管理など、プロジェクトを進行する上できっちりと決めておかないといけない部分を担当しました。

須藤 私はグラフィックデザインとキャラクターデザイン、イラストのほかに、大学時代にUnityなどのゲーム開発のソフトを少し触ったことがあったので、開発を担当いただいた協力会社さんとの窓口も務めました。
張 僕は子どもたちが楽しめる会場の雰囲気をつくるために、タブレットスタンドの装飾やペンキャップなどのプロダクトデザインを担当しました。
鈴木 私はUI・UXデザインを担当しました。タブレットを操作する際の画面遷移やアプリ内の文言、子どもたちが楽しんでもらう体験をデザインするにはどうすればいいかを考える役割でしたね。
プロトタイピングから試行錯誤を重ねたデザインプロセス
まずはどのようなことから制作を進めていきましたか?
赤池 制作に入る前に、展示会などを視察して情報収集を実施したほかに、インクルーシブをテーマとしたワークショップに参加した経験が、その後の制作に活かされていると思います。
森 今回のテーマはインクルーシブデザインに関連があるのではないかと思ったので、インクルーシブデザインを実践している企業にワークショップの開催を依頼しました。
赤池 参加したワークショップでは、ユーザーのペルソナを設定した上でアイデアを発散させ、そこから絞り込んでいく収束のプロセスを経験ができたので、実際に制作に入る際にも、ペルソナを設定した後に今回のテーマである「新しい音の体験」のアイデアを出し合い、3、4個に絞ってからプロトタイプの制作を進めていきました。

須藤 今回の作品のように、ゲームのプロトタイプをすぐにつくるのは難しかったので、かなりアナログな方法でデモンストレーションしたのがおもしろかったですね。100円ショップで買ってきたボールを手に持って動かしながら作品のイメージを伝えるといった、一見すると遊んでいるようなプロトタイピングだったのですが(笑)、普段所属しているデザインチームのメンターやマネージャーなど、様々な方からの率直な意見をもらうことができました。
鈴木 プロトタイプを見た先輩からの指摘で、アイデアがどんどんまとまっていく過程が印象的でしたね。様々な人の声をもらいながら制作を進めていく楽しさを感じることができました。
今回の出展した「らくガッキ」は、子どもたちがタブレットで描いたイラストがスクリーンに映し出され、手をかざして音を鳴らすことができる作品です。 制作過程での苦労はありましたか?
森 実装の場面ではけっこう迷いましたね。
赤池 開発作業を依頼した協力会社の方々と進めていくなかで、プロトタイプの段階では検討していなかった要素がたくさん出てきたので、一日に何度も協議しながら進めていきました。
須藤 協力会社さんとのオンラインの打ち合わせもよくしましたよね。私は子どもの頃からゲームが好きで、自分のなかで気持ちのいいキャラクターのモーションや、音が再生されるタイミングの感覚があったので、こちらの意図が文面だけでは伝わりづらい場面では、動画の資料をつくって画面共有しながら話し合いを重ねていきました。
らくガッキは、体験者が描いた絵に合わせて音が付く仕組みで、しっくりくる音と形の組み合わせを実現するために、たとえば体験者が描いてくれた「丸みのある形」や「角ばった形」などに“っぽい”音をつけた上で、それぞれの音を判定する計算式をつくる必要があったので、選んだ音の基準を決めていく話し合いがいちばん難しかったです。張さんがいろいろと調べてくれたのも助かりました。

張 私自身、プログラミングの知識はないのですが、ChatGPTとかを使っていろいろと試しながら、簡単なデモをつくったりもしましたね。
赤池 それぞれのかたちに対して、自分たちが“っぽい”と感じる音をマッピングすることの妥当性がどこにあるのか分からなかったんですよね。関連する論文にもあたり、波形と音の感性評価について調べてみたところ、感覚的に決めても大きな差がないことがわかったので、最終的には自分たちの感性で決めていきました。
学びながらデザインしていく、自社プロジェクトだからこその経験
最後に、今回のプロジェクトを振り返って感じたことをお聞かせください。
鈴木 子どもたちがモニターの前に立って手を動かしている時のキラキラした表情がとても印象的でした。絵を描いている時は真剣なのですが、自分が描いた絵が大きな画面に表示された時の驚いた顔や、とても楽しそうにしている様子が見られたのがうれしかったです。最初は大きなディスプレイに直接描き込める方があたらしい体験になるかもしれないと考えていたのですが、結果的に2段階に分けたことで、子どもたちに喜んでもらえる体験をつくることができたのではないかなと思います。

須藤 これまで大学でもUXデザインについて学んできましたが、本当にいいものをつくることができるかどうかを確かめる機会がなかったので、今回のように子どもたちからの反応が直接得られる場は貴重だったと思います。
また、会場では子どもたちにアンケートを取ることができたので、Maker Faireで取り組んだことを2本の論文に分けて発表しようと思っています。これまでは社内で論文を出すという動きがあまりなかったようなのですが、私が論文を発表することを社内に共有したところ、興味を持って話しかけてくださる方が何名かいらっしゃって、実際に研究発表に向けての相談をいただくことができました。自分で起こした行動をきっかけに、社内の方が「自分でもやってみよう」と思ってもらえたのが嬉しかったですね。
張 これまで外観のデザインに関わるプロジェクトがほとんどだったので、「らくガッキ」のように、プロダクトに限らないデザインに関わることができたのがよかったと思います。同時に、量産品ではない小さな規模のものづくりを進めていく上での見積もりや発注方法は、普段の業務ではなかなか経験できないことでもあるので、今後活きていくことがたくさんあるのではないかなと感じています。

鈴木 私はインクルーシブデザインのワークショップの経験が印象的でしたね。ペルソナを立ててものをつくることは学生の時にも経験していましたが、今回インクルーシブデザインの知見が得られたことで、Maker Faireの後に関わった研究プロジェクトでも、当事者の方を巻き込みながらデザインを考えていく方法を実践することができました。
森 プロジェクトを通じて、チームで行うものづくりを学ぶことができたと思います。なにかひとつのものをチームでつくることで、メンバーとのコミュニケーションの取り方や、個別で進める部分はどのように取り組んでいくべきなのかなど、学べることがたくさんありました。今回はすべての意思決定を自分たちで行ったので、ゼロからものをつくることの楽しさと大変さを、入社して2年目という早いタイミングで知られたことがよかったなと思っています。
赤池 自分としては、今回のプロジェクトは学びながらつくっていくことができたのが重要なポイントなのかなと感じています。なかなか普段の業務では何種類もツールを試すのは難しいと思うので、学びながら進められる少しの余裕と、当日までに仕上げなくてはならない緊張感の両方を感じることができる、このプロジェクトならではの経験ができたのではないかなと。こうした経験があることで仕事の肌感覚も変わってくると思うので、今後に活かしていきたいと考えています。

Profile
- Suzuka Mori
-
- Ryusei Akaike
-
- Miho Suto
-
- Tenshi Cho
-
- Ayane Suzuki
-